喪主について
-
喪主の役割
喪主はお葬式の最高責任者です。
遺族の中で、故人の遺志を引き継ぎ、葬儀後も故人の供養を中心になって行います。喪主と施主の違い
本来、施主とは「お布施をする主」という意味で喪主をサポートする役割を担います。
「葬儀の費用を負担し、お葬式を運営する責任者」なのです。一般的なお葬式では施主と喪主は兼任であることが多く、ほぼ区別されることがありません。
-
喪主を決める
喪主は、遅くとも通夜の前までに決定しなければなりません。
葬儀において喪主の役割は重要なものですが、基本的に喪主は誰が務めても構わないものです。喪主は遺族の話し合いで決められますが、おもに
- 配偶者
- 直系の子供
- 直系の親族(父母や兄弟姉妹)
- 故人と親しいご友人
といった順で「喪主を務めることが可能な人」が任にあたります。
故人が未成年の場合は、親や兄弟が喪主になることもあります。
最近では、男女の別なく故人といちばん近い人が務めることが多くなっています。
-
喪主の服装

お通夜が始まるまでは、平服(普段の服装)で大丈夫です。
-
女性の服装
女性の方で喪主になられる場合に、着物を着るべきかどうかを悩まれる方も多いかと思います。
地域的なこともありますが、最近では和装と洋装の割合は半々くらいです。アクセサリー類は、結婚指輪以外は基本的にはつけない方がよいとされています。
パールのネックレスかイヤリングのどちらか片方はつけてよいとされています。化粧は控えめに、髪もできるだけシンプルにまとめた方がよいでしょう。
-
男性の服装
羽織と着物、またはモーニングコートが正礼装とされていますが、現在はほとんどの方がブラックスーツを着られます。
ブラックスーツはダブルではいけないと気にされる方がいますが、シングルとダブル、どちらもみられます。
-
喪主の仕事
-
訃報の連絡
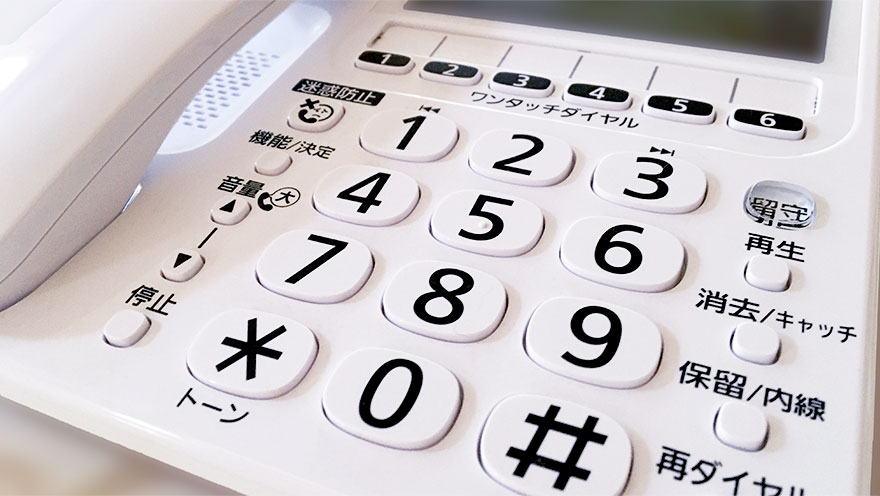
亡くなったことの第一報です。 緊急性を要する連絡ですので、訃報は電話で簡潔に知らせましょう。
電話をする前に必要事項をメモに書いておけば、間違いなくお伝えできます。肉親を亡くした際には、動揺しているかもしれません。
自分で全部しなければと抱え込むのではなく、親族や友人にお手伝いしていただくと良いでしょう葬家に代わって連絡をする方は、必要な内容を簡潔に伝えます。
訃報を誰にどのように伝えるかという決まりはなく、家族の判断で間違いということはありません。
生前の本人の意思やお葬式の規模・関係性を考慮して連絡する方を決め、伝えましょう。連絡方法について
メールやSNSでのお知らせは、人によって見る時間が異なったり受信設定によって届かない場合があります。
電話は出てもらえればすぐに内容が伝わるという点、また、きちんと自分の口から伝えられるという点で一番便利です。
-
連絡をする順番
- 家族や親族などの近親者
疎遠になっている家族や親族がいたとしても、訃報はなるべく迅速に伝えることがよいでしょう。
- (あれば)菩提寺、教会など
- 危篤の際に臨終に間に合わなかった方や、危篤の連絡で駆けつけた方が帰った後に亡くなられた場合は、それらの方々
- 友人や知人・関係者
故人の関係者だけでなく、遺族の知り合いにも連絡をします。
- 近所の方や町内・自治会
近親者以外の方々に連絡の際は、お知らせと併せて生前のおつきあいの感謝もお伝えしましょう。
家族葬など、近親者のみで葬儀をする場合は葬儀後にハガキでお知らせすることもあります。 - 家族や親族などの近親者
-
お伝えすることの例
- 故人の氏名
- 自分と故人の関係
- 死亡日時
- 喪主の氏名
- 通夜と葬儀の日時と場所
- 連絡先
第一報時に決まっていなかったことは、決まった時点で改めて伝えましょう。
新聞のお悔やみ欄などを通した訃報の伝え方もあります。
多くの場合はその手配も葬儀社がしてくれますので相談してみましょう。事前に準備しておくと、もしものときに「あの人に連絡するのを失念していた」ということもなくなります。
エンディングノートなどに連絡先リストを生前からまとめておくと、遺された家族の負担が軽減されます。 -
-
葬儀を主催し、弔問を受ける
喪主は故人に代わって葬儀を主催し、弔問を受けることが役目です。
お葬式の進行は葬儀社と家族の中から選んだ補佐役が段取りをしてくれますので、雑用はあまりせず故人のそばに付き添うようにしてください。
玄関まで見送るのは避けるのがしきたりとなっており、この際は失礼にはあたりません。弔問する参列者ひとりひとりをお迎えしていきますが、丁寧かつ簡潔に対応します。
お悔やみの言葉などに丁重にあいさつをして
「ありがとうございます。故人もさぞ喜んでいることと思います。」
など、簡潔にお礼を述べましょう。 -
葬儀での挨拶

喪主のお葬式における一番の役割が挨拶です。
多忙な中で弔問にかけつけてくれた会葬者の方に、故人に代わりお礼を述べることになります。
通夜式終了時と、告別式終了時には喪主より挨拶をする事が一般的です。特に告別式の挨拶は、最後の挨拶となりますので、最も悲しみが深い時でもあります。
うまく挨拶しようと気がそちらに向かうことよりも、心からありがとうございましたと述べることが大切です。
日頃あまり使わない言葉ということもありますので、紙に書いて読まれる方も多いです。 -
葬儀後のお礼と挨拶回り
喪主は葬儀でお世話になった方へ、お礼の挨拶に出かけます。
(寺院・僧侶、お世話になった町内の方々、故人の勤務先や弔辞を述べていただいた方など)直接訪問できない方には電話で済ませることもありますが、できるだけ直接お礼にうかがいます
相手も気疲れしている場合が多いので、挨拶が済んだら長居をせずに引き上げるのがよいでしょう。 -
その他、葬儀後にすべきこと
-
事務作業の引き継ぎ
会葬者名簿、香典および香典帳、供花・供物帳、弔辞・弔電、会計帳簿、会葬者からの伝言など、事務作業の引き継ぎをします。
-
金銭関係の精算
葬儀の際に支払われた、金銭関係の精算を行います。
-
返礼品などの手配
返礼品や葬儀後に必要なものの手配をします。
-
自宅に訪ねて来られる弔問客への対応
大切な人を亡くした悲しみや、葬儀や葬儀後の手続きで疲弊している状況もありますので、無理のない範囲で対応しましょう。
弔問客の故人への感謝の気持ちやお別れの挨拶をしたい想いに感謝し、温かい対応を心がけます。返礼品について
葬儀で渡した返礼品は一般的には七七日(四十九日)が終わるまで自宅で取っておき、利用した分だけをその後に精算するという流れになります。
そのため、自宅に弔問くださった方にも返礼品をお渡しします。
後日あらためて、いただいたお香典やお供物に応じて返礼品を手配します。
-
さいごに
本当に大変なのはお葬式が終わってから、と言われています。
ご葬儀・法事に関してお困りの際は、桐生典礼会館までご相談ください。
御葬儀・法事に関することは
桐生典礼にご相談ください
-
急なご用命は24時間365日対応
深夜・早朝でも経験豊富な葬儀プランナーが丁寧に対応いたします
- 対応時間
- 年中無休・24時間対応
-
終活・法事など葬儀以外のご相談
相談窓口は下記の通りといたします
- 対応時間
- 平日 月曜日~金曜日 時間9:00~17:00
桐生典礼会館
- ご葬儀
- 家族葬
- 一般葬
- 法 事
- 365日・24時間対応
〒376-0013
群馬県桐生市広沢町5丁目4722

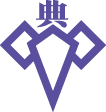
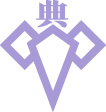

 0277-55-0101
0277-55-0101 0120552601
0120552601